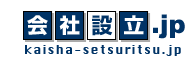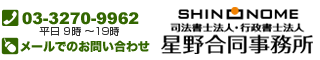トップ > 会社の目的とは?
4. 会社の目的とは?
会社の目的とは、会社が営む具体的な事業のことをいいます。
会社の定款に必ず記載しなければならず、登記事項とされていますので、株主や取引の相手方にとっても会社を識別するための重要なものとなります。
目的の定款記載例(株式会社星野合同事務所の場合)
- 信託業
- 株主名簿管理人業務
- 株式の名義書換、新券引換の取次、株券喪失登録等株式に関する諸手続きの代理業務
- 有価証券保管業務
- その他株式に関する事務の代理業務
- 株主総会の招集、運営等の支援業務
- 経理に関する計算、文書の作成、整理、発送等の代行業務
- 遺言の立案、作成指導、保管及び執行
- 任意後見契約に関する法律の規定に基づく次の業務
- 後見人の法律行為を後見人として代理すること
- 後見人の法律行為を後見人として同意すること
- 後見人の法律行為を後見人として取消すこと
- の他被後見人のために後見人としてなすべき一切の業務
- 意後見監督人として任意後見人を監督する業務
- 前記業務に関するコンサルティング業務
- 株式の売買、企業組織再編、事業譲渡、事業承継等に関するコンサルティング業務
- 株式持株会のコンサルティング業務
- 前記各号に付帯する一切の業務
・目的の数に制限はありません。
・目的の内容に関連性は必要なく、複数の業種でも良いです。
・設立時に営む事業だけでなく、将来営もうとする事業でも目的とすることができます。
・会社の目的については、下記のように適法性、営利性、明確性が求められます。
◆適法性
法律に違反すること、公序良俗に反することを目的とすることはできません(民法第90条)。
×煙草の製造(たばこ事業法第8条)
×麻薬の取引
法令上、弁護士や司法書士等の一定の資格を有する者に限って認められている事業について目的とすることはできません。
×司法書士の事務所の経営(昭27・7・21民事甲1047号回答)
なお、従来「債権取立て」「債権回収」等を目的に掲げる会社の設立は、弁護士法に違反する違法行為を目的に掲げるものとして、登記実務上、認められていませんでしたが、債権管理回収業に関する特別措置法の施行後は、商号中に「債権回収」という文字を用いて、上記の目的を掲げる会社の設立の登記が可能となっています。
◆営利性
会社は利益を追求する営利法人なので、営利性のない目的を定めることはできません。
従前、営利性が認められないとされた例として以下のようなものがあります。
×社会福祉への出資(昭40・7・22民四242号回答)
×政治献金(昭40・7・22民四242号回答)
ただし、当該事業によって利益を得る可能性があれば、公益性の認められる事業であっても、法律で禁止されていない限り、会社の目的とすることができます。
○産婦人科病院経営(昭30・5・10民四100号回答)
◆明確性
目的の記載に用いられている語句が、一般的に理解できることが必要です。
国語辞典や現代用語辞典(現代用語の基礎知識、広辞苑、イミダス等)にその語句の説明が掲載されているか等を参考にして、当該語句が明確性を有するものかどうか判断されます。
従前、明確性を欠くとされた例として以下のようなものがあります。
×不動産取引関連事務代行(昭62・7・13民四3714号回答)
×バラエティ商品の卸・小売(昭44・12・8民四1076号回答)
また、従来、目的の登記にローマ字を用いることはできないという取扱でしたが、ローマ字を含む表記方法が社会的に認知されている語句は、目的の明確性の要請に反しない限り、目的の登記に使用しても差し支えない(平14・10・7民商2364号回答)とされました。
○OA機器、H型鋼材、LPガス、LAN工事、NPO活動等
◆具体性
従前は、具体性を欠くものは、会社の目的として適格性がないとされていましたが、会社法の施行に伴い、会社の目的をどの程度具体的に定めるかは、会社が自ら判断すべき事項であるとされ、会社の設立の登記等において、会社の目的の具体性については、審査を要しない(平18・3・31民商782号通達)ものとされました。
○商業、商取引、運輸業等
ただし、第三者からみて会社の具体的な事業内容が明らかでないと、金融機関から融資を受ける際に審査が通らない場合や取引等において不利益を受ける場合があります。会社がどのような事業をしているのかがわかるように、ある程度具体的に定めておくことが必要です。
不動産業→不動産の売買・賃貸及びその仲介
また、管轄官庁の許認可が必要な業種の場合には、概括的な記載では、許認可が認められない場合があります。目的の中に内容を具体的に記載することが求められることがありますので、注意が必要です。
○一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業
※ここに挙げた先例は会社法施行前のものになります。会社法の施行により目的の適否の判断については、緩和されました。また、法務局の裁量によるところもありますので、事前に確認することをお勧めします。
会社の商号
会社の商号は、原則として自由に選定することができます。 ただし、選定にあたっては、使用可能な文字の制限、法令による制限、商法・会社法の規制や不正競争防止法上の一定の制限がありますので、注意が必要です。
◆株式会社という文字の使用
会社は、その種類に従い、その商号中に「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」または「合同会社」という文字を用いなければなりません(商法第6条2項)。
◆使用することができる文字
商号を登記するには、日本文字のほか、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができます(商業登記規則第50条)。 ローマ字その他の符号としては、ローマ字(AからZまでの大文字及びこれらの小文字)、アラビヤ数字、「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)が該当します。 「( )」(カッコ)を用いた商号の登記は受理されません(昭和54年2月9日民四837号回答)。
◆支店、営業部門を示す文字
会社の商号中に「支店」、「支社」、「支部」、「出張所」、「事業部」、「不動産部」、「出版部」、「販売部」のような会社の支店または1営業部門であることを示す文字を用いることはできません(大10・10・21民事2223号回答、平成14・7・31民商1841通知)(登記研究404号137頁)。 「代理店」、「特約店」という文字を使用することは差し支えありません(昭29・12・21民事甲2613号回答)。
◆法令による制限
銀行、保険会社等は、法令の規定により、その商号中に、「銀行」、「生命保険」等の文字を使用しなければならず、それ以外の者は、その商号に銀行、保険会社等であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとされています(銀行法6条、保険業法7条)。
■法令による制限に抵触するとされた例
・有限会社バンク(昭和45・11・12民四5754号回答)
・株式会社野村保険(昭和53・2・21民四1200号回答)
■法令による制限に抵触しないとされた例
・株式会社データ・バンク(旬刊商事法務1017号44頁)
・有限会社四日市損保事務所(昭43・8・21民四635号回答)
◆類似商号規制の廃止
他人が登記した商号を同一市区町村内において同一の営業のために登記することができないという規制は廃止されました(旧商法第19条、旧商業登記法第27条)。
類似商号規制の廃止により、会社を設立する際に、同一市区町村内において、同一の営業目的で同一又は類似の商号が登記されていないかをあらかじめ調査する必要はなくなりましたので、迅速に会社設立手続きを行うことができます。
◆商法・会社法による規制
同一所在場所における同一商号の登記は禁止されています(商業登記法第27条)。 また、不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号は使用してはならないとされています(商法第12条、会社法第8条)。
◆不正競争防止法上の規制
不正競争防止法では、下記の要件を充たす行為を不正競争と規定しています(不正競争防止法第2条1項1号)。
・需要者に広く認識されていること(周知性)
・商号が同一・類似であること(類似性)
・他人の商品又は営業と混同を生じさせること(混同)
世間に広く認識されている他の会社の商号と類似した商号を使用すると、不正競争防止法上、商号の差し止めや損害賠償請求の対象になる可能性があります。
◆不正競争防止法が問題となった例
×住友林業と住友殖産
住友の表示は一般に広く認識されており、全国的に周知であるということができるとされ、誤認混同を生じるおそれがあると判断されました。
×河原コンクリート工業所(略称河コン)と有限会社カワコン
河コンという略称は、市内の同業者の間ではよく知られており、一定の地域における取引者・需要者の間において広く認識されているものであると判断されました。
×日立マクセル株式会社と株式会社日本マクセル
マクセルという部分が類似するものと認められると判断されました。
○プロフェッショナル・ブレインバンクとプロフェッショナルバンク
両社の商号はブレインの有無において明確に区別され、また、事業が大規模に行われていたものではなく、需要者に周知であったということはできないと判断されました。
類似商号の規制はなくなりましたが、著名な会社の商号や一地方での有名な会社の商号を使用すると業種が違っていても不正競争防止法に抵触し、事後的に商号の差し止めや損害賠償の請求をされるといった可能性がでてきますので、注意が必要です。